

お電話でのお問い合せはこちら
042-674-0855

子宮内膜症とは、子宮の内側を被っている膜(子宮内膜)が、子宮筋層や、卵巣や、腹腔内など、 子宮内膜が本来は存在しないところで、増殖する病気です。 子宮内膜は、卵巣から分泌される女性ホルモンの影響で、月経前は厚くなり、妊娠しなければ、月経時に月経血とともに剥がれ落ちます。 この子宮内膜の一部が、月経時に卵管を逆流し、腹腔内でばらまかれ、そこで定着し、 増殖することが子宮内膜症の原因の一つと考えられます。子宮内膜が定着した場所で、月経時に出血を繰り返し、 癒着や疼痛の原因になります。 子宮筋層内に発生すれば、子宮腺筋症といって、子宮が腫大します。卵巣で発生すれば、チョコレートのう腫といって、 卵巣にチョコレート様の液がたまって、卵巣が腫大します。 子宮後壁に子宮内膜症が発生すると、子宮と直腸が癒着し、 子宮後屈となり、月経痛や、性交痛、排便痛の原因となります。
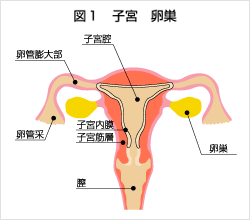
子宮内膜症の原因は、はっきりとはわかっていません。月経時に、子宮内膜が月経血とともに逆流し、 卵管を通って腹腔内にばらまかれ、定着、増殖するという説が受け入れられています。 子宮内膜症は女性ホルモンに依存し、20-30歳で発症する事が多く、女性ホルモンが活発な20-40歳代では、 子宮内膜症の病巣が少しずつ広がる可能性があります。
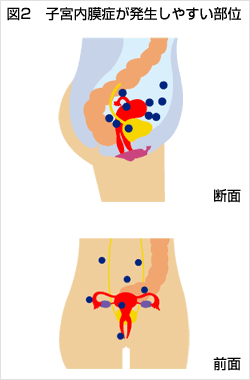
月経痛、月経量が多い、性交痛、排卵痛、月経時以外の下腹痛、不正出血、排便痛 などです。
女性ホルモンに依存しているので、去年より今年のほうが症状が強いというように、年々症状が次第に悪化する事が特徴です。
また、不妊症の原因としても、子宮内膜症は重要な位置をしめています。子宮内膜症の方の約20-30%が不妊症を合併しています。
年々子宮内膜症の方は、増加していると考えられます。初経年齢の若年化、食生活の欧米化、
少子化により出産回数が減り月経回数が増加していることなどが、原因としてあげられています。これからも、子宮内膜症の方は増加していくと考えられます。
月経のある女性のうち、症状の程度の差はありますが、10%位の方が子宮内膜症に罹っていると推定されます。
子宮内膜症の臨床診断は、通常外来で、患者さんから症状を聞く問診、内診、血清マーカー検査(採血)、超音波検査、MRIの検査で行なわれています。 しかし、確定診断をつけるためには、直接病巣の広がりを目で確かめる必要があります。そのためには、腹腔鏡や、開腹手術が必要です。 しかし、子宮内膜症を疑うすべての人に開腹手術や腹腔鏡を行なうのも困難なので、臨床的に診断して薬物治療を開始する事もおこなわれています。
子宮内膜症の治療は、手術療法と薬物療法があります。
患者さんの年齢、妊娠を希望しているかどうか、月経時の痛みの強さや、病巣の広がりなどで治療法を選択します。
a.点鼻薬または注射
一時的に身体を更年期の状態にして、卵巣からの女性ホルモンの分泌を低下させて、病巣を縮小させる治療法です。使用によって更年期の症状がでることがあります。
b.内服薬
男性ホルモン系の薬で、卵巣からの女性ホルモンの分泌を抑制し、病巣を縮小させる治療法です。使用によってにきびができたり、体重が増加することがあります。
c.経口避妊薬
低容量ピルや中容量ピル