

お電話でのお問い合せはこちら
042-674-0855

骨粗しょう症とは、骨量が減って、骨がスカスカになり、骨折しやすくなる骨の病気です。
骨量は、年齢とともに確実に減少します。骨は、硬くて変化してないようにみえますが、実は、皮膚と同じように日々新陳代謝をしています。 骨の中のカルシウムが血液に溶け出す(骨の破壊)一方で、血液からカルシウムが補給されて骨が作られています(骨の形成)。 年齢とともに、骨が破壊されるほうが、作られるよりも上回るようになるので、骨量が下がります。
女性は骨粗しょう症になりやすいといえます。 女性ホルモンには、骨を形成する働きがあります。 女性が閉経を迎え、女性ホルモンが急激に下がると、骨量も急激に下がり、骨粗しょう症になりやすくなります。
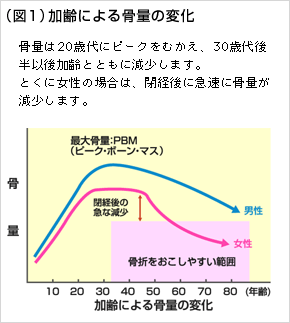
骨粗しょう症の主な症状は、背中が丸くなる、腰が曲がる、背が縮むなどです。
これは、背骨が骨粗しょう症によって、もろくなって、自分の体重で、変形(骨折)しているのです。
その他、骨粗しょう症になると、足の付け根や、腕、手首なども、転倒などの簡単なことで、骨折しやすくなります。
また、骨粗しょう症は、骨量の減少だけで自覚症状がないこともあります。
骨粗しょう症になると、骨折しやすくなります。特に、足の付け根の骨折は、寝たきりの原因になります。
高齢化社会で問題となる寝たきりの原因の第1位は脳卒中、第2位は骨折です。寝たきりになると、Q.O.L(生活の質)が著しく低下し、
またいろいろな病気を合併し、死亡率が高まります。
ですから、豊かな高齢期を過ごすために、骨折の予防、つまり骨粗しょう症にならないようにすること、そして、仮に骨粗しょう症になったとしても、骨折しないように早期診断、早期治療が大事です。
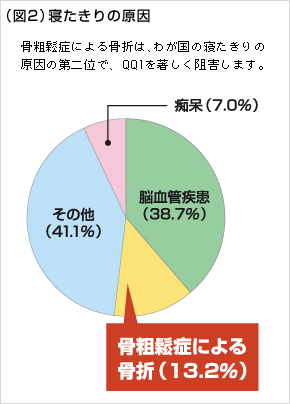
骨粗しょう症と診断されたら、治療により骨量の減少を食い止め、骨量を増やし、骨折を防ぐことが大事です。
更年期以降の女性では、女性ホルモンが低下しており、食事や運動だけでは骨量の回復が難しいことが多く、その場合は薬物療法が必要となります。骨粗しょう症の薬には、右図のものがあります。
骨粗しょう症の治療では、生活習慣病のように、治療が長期間に渡ることがあります。治療中は効果をみるために、定期的に骨量を測定しましょう。
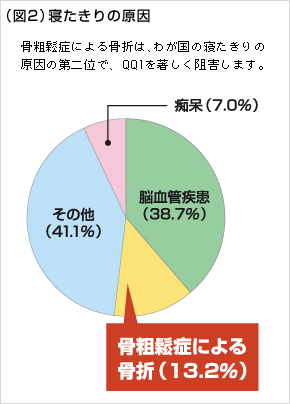
日ごろから、カルシウムの多い食事をし、歩くなどの運動を心がけましょう。また、骨粗しょう症になると、転倒などで、簡単に骨折するので、まず、転倒を防ぐこと大切です。
女性は、閉経後、骨粗しょう症になりやすいといえます。しかし、骨量の減少だけでは、自覚症状がないことがあります。ですから、骨粗しょう症の予防のために、現在自分がどのくらいの骨量なのか、検査を受ける事をお勧めします。