

お電話でのお問い合せはこちら
042-674-0855

卵巣は子宮の両側に左右1つずつあり、親指の頭くらいの大きさです。(図1) 卵巣は上皮に被われていて、その直下に多数の卵胞が存在します。(図2) 卵胞は、ホルモンを産生する性索間質と、卵子の元になる卵細胞(胚細胞)から成っています。 卵巣の働きは、女性ホルモンを分泌することと、卵細胞を成熟させて排卵することです。
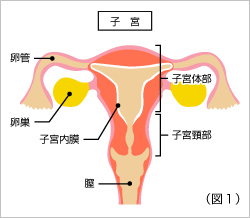
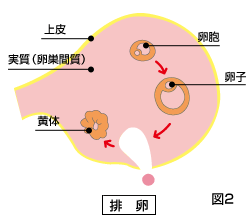
卵巣は、上皮と卵巣実質、性索間質、卵子からなり、それらすべての部位から腫瘍が発生するため、数多くの腫瘍が発生します。 それぞれ、良性、境界悪性、悪性の腫瘍が発生します。卵巣がん(悪性)は、卵巣腫瘍全体の10パーセント位です。 卵巣がんの代表的なものは、表層上皮や卵巣間質細胞から発生する、しょう液性腺がん、粘液性腺がん、類内膜腺がんで、多くは 50歳代にみられます。粘液性腺がんは、若い人にも発生することがあります。 そのほか、ホルモンを産生するがんや、胃がんや大腸がんから転移する転移性卵巣がんもあります。
卵巣がんの発生率は、欧米の3分の1くらい(年間5000)といわれています。 最近日本人女性の発生率の増加が注目されています。 卵巣がんの発生の危険因子の1つとして、排卵の回数があげられます。排卵とは、卵巣から卵子がとび出る現象です。 排卵のたびに卵巣上皮が傷つけられ、修復されています。この損傷と修復を繰り返す過程で、がんが発生すると考えられています。 現代の日本の女性は、子供を産む回数が減り、また初経から閉経までの期間が長くなっているため、昔に比し排卵の回数が増えて います。このことが、卵巣がんが増えている事と関係していると思われます。避妊薬のピルは排卵を抑制するため、長期に服用す ると、卵巣がんの発生の危険度が下がります。
卵巣にできた子宮内膜症から、卵巣がんが発生することが分かってきました。 類内膜腺がん、明細胞がんが関係しています。特に45歳以降から卵巣がんの発生が増えてきます。 そこで、子宮内膜症で卵巣が腫れている(チョコレートのう腫)人は、閉経以降、子宮内膜症の症状(月経痛や、月経過多など) がなくても、定期的に卵巣のチエックを、経膣超音波検査で受けるのが良いでしょう。
卵巣は骨盤の奥深くに存在するため、卵巣がんはかなり大きくなるまで、症状が出にくいといえます。 卵巣がんは、自覚症状もなく進行し、下腹部痛や、下腹部膨満感、下腹部のしこりといった症状が出た時には、かなり悪化してい ることが多いので、サイレントキラー(沈黙の殺人者)といわれています。また、卵巣は2つあるため、片方にがんが発生しても、 もう片方が正常に機能していれば、月経異常や、不正出血などの症状も見られないため、発見が遅れがちになります。
卵巣は骨盤の奥にあるので、子宮と違って、直接細胞や組織を採取することはできません。診察時、卵巣が腫れていれば、経膣超 音波検査を行い、さらにくわしく調べるために、MRIや腫瘍マーカー(血液検査)を行います。そして最終的には、手術により卵 巣を摘出して、初めて組織学的にがんと診断されます。卵巣がんは早期には症状が出にくいため、症状が出てから精査した場合に は、卵巣がんは進行している事が多いと言えます。また、急速に進行するがんもあるので、1年に1回診察していても、発見が難 しいがんもあります。しかし、そうとは言っても婦人科検診の際に、経膣超音波検査を受けることは、より早く卵巣がんを発見す ることにつながると思います。
卵巣がんの治療はまず手術を行い、完全に摘出されなくても、できる限り腫瘍を取りはぶき、その後、抗がん剤の治療を行うのが 基本です。早期に発見されれば、生存率も高くなります。